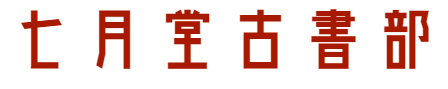-

夜明けと音楽 / イ・ジェニ、橋本智保 訳【新本】
¥2,200
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 「結局のところ物を書くというのは、よく知っている単語の中に、自分の悲しみを見つけること」 なくなったものの痕跡をたどり、孤独とともに創作する詩人イ・ジェニが綴るエッセイ集。 夜の闇に流れる、長く静かな時間に立ち上がる静謐な26編。 ある夜明けには涙のようにあふれる音楽について語り、またある夜明けには悲しみに満ちたプレイリストを思い出しながら詩を読む。 旅先で遭った不慮の事故、長いあいだ不眠症に悩まされたこと、ロックバンドで音楽に心酔していた二十代の頃のこと。 孤独とともに創作する詩人が、母の最期に立ち会い、イヨネスコやボードレールなど文人たちの足跡をたどり生まれた、詩と散文の境界を行き来するような言葉の記録。 ロングセラーエッセイ『詩と散策』(ハン・ジョンウォン)と並ぶ、“言葉の流れ”シリーズの代表作。 ①「チェチェク―花の別称」 ②「夢はどこから流れてきて、どこへ流れていくのか ――夜明けの日記 二〇一六年二月七日 一時三十一分」 ③「白紙は削除された文章を抱いている」 『夜明けと音楽』は、時間の流れという出版社の「言葉の流れ」シリーズ全十巻の十巻目にあたり、本書はその全訳です。しりとりをするように前の著者が次の著者に言葉をバトンタッチをする形を取っており、四冊目の『詩と散策』(ハン・ジョンウォン、拙訳 二〇二三年 書肆侃侃房)から『散策と恋愛』へ、『恋愛と酒』から『酒と冗談』へ、『冗談と影』から『影と夜明け』へ、そして最後を詩人イ・ジェニの『夜明けと音楽』が飾ります。(訳者あとがき) 【著者プロフィール】 イ・ジェニ 이제니 1972年生まれ。2008年、京郷新聞新春文芸によりデビュー。詩集『たぶんアフリカ』『なぜなら、私たちは自分を知らなくて』『流れるように書いたものたち』『ありもしない文章は美しく』を発表。片雲文学賞優秀賞、金炫文学牌、現代文学賞を受賞。 言葉によって世界の細部を書き、消し、再び書くことをとおして、既知の世界と少しは違う世界、少しは広く深い世界にたどり着くことを願っている。 【訳者プロフィール】 橋本智保(はしもと・ちほ) 1972年生まれ。東京外国語大学朝鮮語科を経て、ソウル大学国語国文学科修士課程修了。 訳書に、キム・ヨンス『夜は歌う』『ぼくは幽霊作家です』『七年の最後』(共に新泉社)、李炳注『関釜連絡船』(藤原書店)、朴婉緒『あの山は、本当にそこにあったのだろうか』(かんよう出版)、ウン・ヒギョン『鳥のおくりもの』(段々社)、クォン・ヨソン『レモン』(河出書房新社)『春の宵』(書肆侃侃房)、チェ・ウンミ『第九の波』(書肆侃侃房)、ハン・ジョンウォン『詩と散策』(書肆侃侃房)、チョン・ジア『父の革命日誌』(河出書房新社)など多数。 【目次】 Ⅰ 音楽もしくは孤独、あるいは愛と呼んでいた瞬間 チェチェク―花の別称 涙のようにあふれ出る音楽 誰かがあなたのために祈りを捧げる 文章は上から下へ降り注ぐ 跳躍する曲線があるから、私たちは メタリカフォーエバー その光が私のもとへやってくる 夢はどこから流れてきて、どこへ流れていくのか 事物に慣れた目だけが事物の不在を見る 回復期の歌 私の部屋の旅行―天井と床のあいだで一週間 麻田―繰り返し広がる 夜釣りのためのプレイリスト 眠れない夜のためのプレイリスト Ⅱ 再び明るむ夜明けのリズムから 未知の書き物 夢から来た手紙―天上の音を歌うあなたへ 直前の軌跡 夜明けに詩を読むあなたに 暗闇の中から暗闇に向かって イメージは言語を必要とする 言葉が魂へ流れたら 紙の魂 白紙は削除された文章を抱いている 墓地を散策する人の手紙 瞬間の中から、瞬間に向かって 朝の木から夜明けの海まで 日本の読者のみなさんへ 訳者あとがき 著者 イ・ジェニ 訳者 橋本智保 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年11月20日 四六判変形 240ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

現代短歌パスポート6 石になるための準備号【新本】
¥1,100
【出版社内容紹介】 大好評の書き下ろし新作短歌アンソロジー歌集、最新刊! 山田航 藪内亮輔 竹中優子 田村穂隆 石川美南 土岐友浩 小坂井大輔 左沢森 小原奈実 笹川諒 【収録作品】 田村穂隆「構想」 土岐友浩「タイムアタック」 石川美南「サイレント菜園」 左沢森「This Car Is Very You」 竹中優子「半額のシール」 小坂井大輔「涅槃は坊主の耳の奥です」 小原奈実「鷹の墓」 藪内亮輔「それでも表示する」 笹川諒「宇宙樹」 山田航「それぞれのちゃちな忘却のために」 【執筆者プロフィール】 田村穂隆(たむら・ほだか) 一九九六年生まれ、島根県出身。「塔」所属。第一歌集『湖とファルセット』(現代短歌社)で第四十八回現代歌人集会賞、第六十七回現代歌人協会賞を受賞。 土岐友浩(とき・ともひろ) 一九八二年、愛知生まれ。歌集に『Bootleg』(第四十一回現代歌人集会賞受賞)、『僕は行くよ』、『ナムタル』。「西瓜」同人。京都市在住。 石川美南(いしかわ・みな) 一九八〇年生まれ。同人誌pool および[sai]、さまよえる歌人の会などで活動中。歌集に『砂の降る教室』『裏島』『離れ島』『架空線』『体内飛行』。第一回塚本邦雄賞受賞。趣味は「しなかった話」の蒐集。 左沢森(あてらざわ・しん) 一九八五年生まれ。山形県出身。二〇二一年ブンゲイファイトクラブ3優勝。二三年第五回笹井宏之賞大賞受賞。第一歌集準備中。 竹中優子(たけなか・ゆうこ) 一九八二年生、福岡県在住。短歌・詩・小説を書く。歌集『輪をつくる』(KADOKAWA)、詩集『冬が終わるとき』(思潮社)、小説『ダンス』(新潮社)。 小坂井大輔(こざかい・だいすけ) 一九八〇年名古屋市生まれ。短歌ホリック同人。二〇一六年「スナック棺」で短歌研究新人賞候補。歌集に『平和園に帰ろうよ』『KOZAKAIZM』。 小原奈実(おばら・なみ) 一九九一年東京生まれ。第五十六回角川短歌賞次席。東京大学本郷短歌会(現在は解散)、同人誌「穀物」などに参加。歌集に『声影記』(港の人、二〇二五年)。 藪内亮輔(やぶうち・りょうすけ) 一九八九年生まれ、京都在住。第一歌集『海蛇と珊瑚』(二〇一八年・角川文化振興財団)、第二歌集『心臓の風化』(二〇二四年・書肆侃侃房)。角川短歌賞選考委員。 笹川諒(ささがわ・りょう) 長崎県生まれ。大阪大学文学部卒業。二〇一四年より「短歌人」所属。第一歌集『水の聖歌隊』(書肆侃侃房、二〇二一年)、第二歌集『眠りの市場にて』(書肆侃侃房、二〇二五年)。 山田航(やまだ・わたる) 一九八三年札幌市生まれ・在住。「かばん」会員。第一歌集『さよならバグ・チルドレン』(現代歌人協会賞・北海道新聞短歌賞受賞作)が二〇二五年九月に書肆侃侃房「現代短歌クラシックス」シリーズで新装復刊。 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年11月20日 四六判変形 112ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

午後のコーヒー、夕暮れの町中華 / 安澤千尋【新本】
¥1,980
【出版社内容紹介】 いつだってわたしを助けてくれたのは、街にある小さな店だった。 そこへたどり着けさえすれば、またわたしは生きる力を取り戻すのだ。 街歩きエッセイスト「かもめと街 チヒロ」が、東京の店の情景を描く。 浅草、上野、日本橋、銀座、新橋、神保町、秋葉原 ――東京下町エリアを中心とした全61店 【目次より】 揚げたてのチキンバスケット ― 銀座ブラジル 浅草店(浅草) 夢うつつの空間で、クリームソーダ ―丘(上野) はじめまして、黒い天丼 ― 天ぷら 中山(日本橋) 平日のサラリーマンとポンヌフバーグ ― カフェテラス ポンヌフ(銀座・新橋) 喪失と再生のグラタントースト ― カフェトロワバグ(神保町・神田) 【著者プロフィール】 安澤千尋(やすざわ・ちひろ) 1981年生まれ。浅草出身の街歩きエッセイスト。2017年より個人ブログ『かもめと街』を始める。『決めない散歩』『いつかなくなるまちの風景』『たらふく』などの日記やエッセイ、アンソロジーなど多岐にわたるZINEを発行。近年では青土社『ユリイカ』、講談社『群像』への寄稿などで活動し、本書が初の商業出版となる。 著者 安澤千尋 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年5月13日 四六判 224ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

現代短歌パスポート5 来世イグアナ号【新本】
¥1,100
【出版社内容紹介】 大好評の書き下ろし新作短歌アンソロジー歌集、最新刊! 斉藤斎藤 山崎聡子 堀静香 吉田隼人 井上法子 佐々木朔 石井僚一 丸山るい 野口あや子 内山晶太 【収録作品】 佐々木朔「新市街」 井上法子「碧瑠璃」 丸山るい「遠景」 堀静香「ひらひらと四股」 野口あや子「サブスク」 内山晶太「逃げてゆく馬たちの」 山崎聡子「越冬隊」 斉藤斎藤P「呼吸のように」 吉田隼人「nunc aeternum」 石井僚一「ありがとアーメン、さよならグッバイ」 【執筆者プロフィール】 佐々木朔(ささき・さく) 1992年神奈川県生まれ。早稲田短歌会を経て、現在「羽根と根」同人。歌集に『往信』(2025年、書肆侃侃房)。 井上法子(いのうえ・のりこ) 1990年生まれ、福島県出身。著書に『永遠でないほうの火』『すべてのひかりのために』(ともに書肆侃侃房)。 丸山るい(まるやま・るい) 1984年生まれ、東京都在住。「短歌人」所属。第22回髙瀬賞受賞。第一歌集準備中。 堀静香(ほり・しずか) 1989年神奈川県生まれ、山口県在住。短歌同人「かばん」所属。第一歌集『みじかい曲』(2024年、左右社)で第50回現代歌人集会賞受賞。他エッセイ集に『わからなくても近くにいてよ』(2024年、大和書房)など。 野口あや子(のぐち・あやこ) 1987年、岐阜市生まれ。「未来」所属。第一歌集『くびすじの欠片』にて第54回現代歌人協会賞。ほか歌集に『夏にふれる』『かなしき玩具譚』『眠れる海』。岐阜新聞にて月一エッセイ「身にあまるものたちへ」連載中。 内山晶太(うちやま・しょうた) 1977年、千葉県生まれ。第57回現代歌人協会賞。歌集に『窓、その他』。「短歌人」編集委員。「pool」「外出」同人。 山崎聡子(やまざき・さとこ) 1982年栃木県生まれ。「pool」、ガルマン歌会などに参加。未来短歌会所属。2013年歌集『手のひらの花火』(短歌研究社)で第14回現代短歌新人賞。2021年歌集『青い舌』(書肆侃侃房)を刊行。2022年同歌集で第3回塚本邦雄賞。 斉藤斎藤P(さいとう・さいとうぴー) ・斉藤斎藤(さいとう・さいとう) 1972年生まれ。歌集『渡辺のわたし』『人の道、死ぬと町』。 ・ChatGPT 4o(ちゃっとじーぴーてぃー・ふぉーおー) 2023年生まれ。豊富知識で対話の疑問を即解決する最新AI。 吉田隼人(よしだ・はやと) 1989年、福島県出身。早稲田大学大学院仏文科博士課程満期退学。2013年に角川短歌賞、2016年に現代歌人協会賞。歌集『忘却のための試論』『霊体の蝶』、エッセイ集『死にたいのに死ねないので本を読む』。 石井僚一(いしい・りょういち) 1989年北海道生まれ。石井は生きている歌会主催。歌集に『死ぬほど好きだから死なねーよ』(短歌研究社)、『目に見えないほどちいさくて命を奪うほどのさよなら』『・』(いずれもKindle版)。 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年4月28日 四六判変形 112ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

葛原妙子歌集【新本】
¥2,200
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 戦後短歌史に燦然と輝く歌人・葛原妙子。 すべての歌集から1500首を厳選、 葛原の壮大な短歌世界を堪能できる一冊。 著者 葛原妙子 編者 川野里子 発行所 書肆侃侃房 発行日 2021年11月19日 四六判 296ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

寂しさでしか殺せない最強のうさぎ【新本】
¥2,200
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 雨宿りやめる決意を君はする止んだのか濡れる気かは知らない 小説的な企みのなかに、「ひかりってめにおもい」ことや「夏が動く音」、「手渡し」の危険さといった日常に潜むスリルが散りばめられている。 ふいに出現する口語の息遣いに虚をつかれた。 ――江國香織 【収録歌より】 猫の頭蓋骨は小さい 手に収まるくらいの量の春つかまえる 手渡しは危ないからさテーブルに置くよ紅茶もこの感情も ひかりってめにおもいの、と不機嫌だごめん寝てるのに電気つけちゃって 電線で切り刻まれた三日月のひかりが僕をずたずたに照らす 海、海、海、海が見えるよ僕たちは海に奇跡の投げ売りを見た 著者 山田航 装幀 クラフト・エヴィング商會 発行所 書肆侃侃房 発行日 2022年7月20日 四六判変形 144ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

初恋 / 染野太朗【新本】
¥2,420
【出版社内容紹介】 悲しみはひかりのやうに降(ふ)りをれど会ひたし夏を生きるあなたに 恋の悲しみも苦しみも嫉妬も ただひたすらに 会いたい 伝えたい 狂おしい胸の裡に吞み込んで、ただ歌を 2023年6月下旬発売 【収録歌より】 ああなんでこんなに傷つけたいのだらうしじみ汁ずずずと啜りたり 恋のやうに沈みつつある太陽が喉をふさいでなほ赤いんだ しあはせのきみにかかはることできず冬が去る雨のすくなかつた冬 四月二日物干し竿を光ごとぬぐつてぼくは布団を干した 嫉妬を投げつけてほしかつた茶碗とか花瓶とか小銭のごとく 【著者プロフィール】 染野太朗(そめの・たろう) 1977年茨城県生まれ、埼玉県に育つ。 歌集に『あの日の海』(本阿弥書店、2011年)、『人魚』(角川書店、2016年)、現代短歌クラシックス『あの日の海』(書肆侃侃房、2021年)がある。 短歌同人誌「外出」「西瓜」同人。短歌結社「まひる野」編集委員。 著者 染野太朗 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年7月11日 四六判 160ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

青い舌【新本】
¥2,310
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 第3回塚本邦雄賞受賞!! 舌だしてわらう子供を夕暮れに追いつかれないように隠した 子供との時間のなかに 前世のような記憶の翳がさす。 いつか、どこかで、わたしは立っていた 2021年7月刊行。 【自選5首】 君のべろが煙ったように白かったセブンティーンアイスクリーム前 西瓜食べ水瓜を食べわたくしが前世で濡らしてしまった床よ 蟻に水やさしくかけている秋の真顔がわたしに似ている子供 ヒメジョオンの汁でつくったマニキュアでにぶく光っていた爪の先 遮断機の向こうに立って生きてない人の顔して笑ってみせて 【著者プロフィール】 山崎聡子(やまざき・さとこ) 1982 年栃木県生まれ。 早稲田大学在学中に作歌を始め、2010 年「死と放埓なきみの目と」で 第53回短歌研究新人賞受賞。 2013年第1歌集『手のひらの花火』( 短歌研究社) で第14 回現代短歌新人賞受賞。 2022年『青い舌』で第3回塚本邦雄賞受賞。 pool、「未来」短歌会所属。 著者 山崎聡子 発行所 書肆侃侃房 発行日 2024年5月23日(第2刷) 四六判変形 160ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

世界同時かなしい日に / 山下一路【新本】
¥2,200
【出版社内容紹介】 世界同時かなしい日に雨傘が舗道の上をころがる制度のような驟雨 2023年に亡くなった山下一路の作品を有志がまとめ、第二歌集『スーパーアメフラシ』(2017年)以降に発表された歌を中心に編まれた遺歌集。 「山下短歌は、人々が日常生活を最優先する中で「考えなくなっている事柄」を寓意的にではありますが伝えようとしています。文体こそ軽みを持っていますが、本人はちっともは面白がらず、溜飲も下げず、深く悲しんでいるようです。それは絶望と紙一重だったかもしれません」(編者あとがきより) 「これからたくさん軽口を叩かれ、笑ったり、苦笑(にがわら)ったりの前に、一回ちゃんと泣かされる。山下さん。(略)軽(かろ)みでもって最後まで駆け抜けた先達には「かばん」だと杉﨑恒夫がいるし、口語の抜け感では岡井隆、暗喩の質感だと平井弘、「この人は本当に、どういうつもりなんだろう」の楽しさからはしんくわが連想される。(略)なんて厄介なものを置いていったんだ」 ─────────伊舎堂仁(栞より) 【栞】 伊舎堂仁「二周目の前に」 坪内稔典「はははぽちゃぽちゃ」 【収録歌より】 この星に投身をする少女のように海底へ降りてゆくレジ袋(題詠: 塵も積もれば山となる) 水銀の海に溺れてユニクロの試着室から出られぬアリス(題詠:鏡) これは食べ物ではありません口から溢れだす倫理です ないよりはだいぶいい虫コナーズ ぶらさげているヒロシマの鐘 ふらふらと母飛んできて蛍光す説明ばかりの映画みたいに 【目次】 Ⅰ 世界同時かなしい日に 世界同時かなしい日に 浜辺 で、蛸になる(抄) プラスチックの米櫃のなかで(抄) Ⅱ 世界同時晴れた日に 昭和レジデンス ぷぷプリン体 そんなところがキライ ぬらりひょんと一緒 ロング・グッドバイ 太陽政策 緘黙教団 We selected a mass suicide エリー・マイラブ 2040年 ビーマイベイビー あらかわ遊園 この国は賛同しません Ⅲ 新しい戦争がはじまる 新しい戦争がはじまる エビデンスがほしいんだよ スワンボート水没ちゅう もうすぐですね きょうも新聞はお休みです カンナとゴジラ ローカルな話しで恐縮ですが 世界同時晴れた日に Ⅳ ジンタカタッタカタン ジンタカタッタカタン 魚の目に花粉症 レーゾン・レプリカ コロナの星でおぼれる あるある公園で エレーンは元気ですか 武勇でんででんでんでん 東京天使病院 お取り寄せの世界 Ⅴ 舟を出す日に サフラジェット記念日 スーパームーンの夜に キューちゃん スーパーアルプスで買い物をした夜にキミと話した ただしい資本主義について ぎなのこるがふのよかと 無呼吸症候群の夜 やがて(外付け) カラフルペイント 舟を出す日に 増強・増強・増強 Ⅵ 全世界同時夕焼け 赤いハンカチの王国 勝鬨橋から 鳥は川面をわたって お持ち帰りにします この星に 全世界同時夕焼け 『あふりかへ』抄 『スーパーアメフラシ』抄 出典一覧 編者あとがき(飯島章友) 山下一路略歴 【著者プロフィール】 山下一路(やました・いちろ) 1950年3月14日生。中央大学在学中に全共闘に参加。闘争中なだれ込んだ校舎の壁に大書された福島泰樹の短歌を見たことが短歌との出会いとなった。氷原短歌会に参加。1976年に第一歌集『あふりかへ』(視原社)刊行。その後は企業戦士となって夜討ち朝駆けの生活を送る。50代なかば、過労によるものか心身を患い退職。短歌を再開。2006年10月号から「かばん」に参加。「かばん」を活躍の場としつつ、並行して2013年にはスワンの会にも参加。また、岡井隆の講座にも通うなど研鑽に努め、独自の表現を究めていく。2017年に『スーパーアメフラシ』(青磁社)刊行。2023年3月28日脳梗塞で緊急搬送され、4月9日永眠。享年73。 著者 山下一路 発行所 書肆侃侃房 発行日 2024年11月16日 四六判 208ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

大江満雄セレクション【新本】
¥2,200
【出版社内容紹介】 ぼくらを感激さすものは ぼくら自身がつくらねばならぬ (「雪の中で」より) ハンセン病療養所の入所者による合同詩集『いのちの芽』を編んだ詩人大江満雄の代表的な仕事を精選した作品集。 プロレタリア詩運動の中心で活躍した後、戦争詩の時代を経て、戦後の激動期を生き抜いた大江満雄。常に混交のなかに身を置き、社会の片隅で生きる人たちへのあたたかいまなざしにあふれた作品群を残した。単行本初収録作品を含む詩63篇と散文8篇を収録する。 「大江満雄は、多様で異質な人たちが、どうすれば互いに理解し合うことができるかを探究した詩人だ。他者との相互理解に至るために、独自の詩の世界を切り拓き、新たな対話思想を展開した。その詩学の輝きは、現在も魅力を失っていない」(編者解説より) 2025年3月上旬発売予定です。 【目次】 詩(「日本海流」「四万十川」「四方海」「癩者の憲章」ほか63篇) 散文(「詩の絶壁」「ライ文学の新生面」「日本思想への転向者フェレイラ」ほか8篇) 編者解説 編者あとがき 大江満雄年譜 【著者プロフィール】 大江満雄(おおえ・みつお) 1906年高知県生まれ。詩人。10代で父とともに上京。原宿同胞教会にて受洗。詩を書き始める。プロレタリア文学運動の中心で活躍。そのため治安維持法違反で検挙、転向。以後、戦争詩を書く。戦後はヒューマニズムを基調とする思想的抒情詩を多数発表した。詩集に『血の花が開くとき』(1928年)、『日本海流』(1943年)、『海峡』(1954年)、『機械の呼吸』(1955年)、『自選詩集 地球民のうた』(1987年)。その他、ハンセン病療養所入所者の合同詩集『いのちの芽』編集、解説。多くの評論、児童文学の作品ものこした。1991 年心不全により死去。享年85。没後、『大江満雄集―詩と評論』(思想の科学社、1996年)が刊行された。 【編者プロフィール】 木村哲也(きむら・てつや) 1971年生まれ。国立ハンセン病資料館学芸員。2023年に企画展「ハンセン病文学の新生面 「いのちの芽」の詩人たち」担当。『詩集 いのちの芽』(岩波文庫、2024年)解説を執筆。著書に『『忘れられた日本人』の舞台を旅する──宮本常一の軌跡』(河出文庫、2024年)、『来者の群像──大江満雄とハンセン病療養所の詩人たち』(編集室水平線、2017年)、編著に『内にある声と遠い声──鶴見俊輔ハンセン病論集』(青土社、2024年)など。 公式オンラインストア Amazon 著者 大江満雄 編者 木村哲也 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年3月13日 四六判 264ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

王国を見にいくと言い残して / 蝦名泰洋【新本】
¥2,200
【出版社内容紹介】 失ってはならない涙と 消えない光がある 傷つきやすいこの世界に詩人がいてくれてうれしい わたしは蝦名さんの詩や短歌を読んで生きてこられた ―野樹かずみ ひっそりと生き、亡くなった蝦名泰洋の幻の詩集 『カール ハインツ ベルナルト』ほか、詩人の全貌 王国を見にいくと言い残して もどらない彼のことを パンを食べているとき忘れていた 食べるときは忘れているのだ たえまなく浸食される時間の痛みの中で わたしも一筋の傷口である 黒パンには塩分が含まれており 沁みる 王国はどうだったの? と、もどって来たら訊いてみよう (カムパネルラ忌より) 【著者プロフィール】 蝦名泰洋(えびな・やすひろ) 1956年 5月20日 青森市に生まれる。 青森高校卒業。明治大学卒業。数年東京で働いたのち青森に帰郷。 1985年頃から短歌をつくりはじめる。90年頃から98年頃、短歌や詩を投稿、発表し、注目される。 「短歌研究」新人賞候補、評論賞候補(1991年) 青森県文芸協会新人賞(1992年) 東北デーリー デーリー歌壇年間賞(1993年) 青森県芸術文化奨励賞(1994年) など。 1993年 歌集『イーハトーブ喪失』(沖積舎)刊行。 1994年 詩集『カール ハインツ ベルナルト』(筆名・伊丹イタリア 私家版) 1995年 『現代短歌の新しい風』(ながらみ書房)に「イーハトーブ喪失」から50首掲載。 1999年 青森を離れる。茨城県内に職を得て2009年まで働く。 2010年 東京に移る。台東区に住み職を得る。 2020年 春頃から腰痛。10月駒込病院で尿管癌と診断される。治療後、12月に退院。 2021年 3月、両吟歌集『クアドラプル プレイ』の構想を野樹に伝える。3月から6月にかけて『ニューヨークの唇』180首をまとめる。6月末、杏雲堂病院に入院。 2021年 7月26日 永眠。 2021年 9月 両吟歌集『クアドラプル プレイ』(野樹かずみとの共著 書肆侃侃房)刊行。 2023年 6月 歌集『ニューヨークの唇』(書肆侃侃房)刊行。 『クアドラプル プレイ』の著者略歴から 子供時代、詩を書きたいと願う。書けない。高校生のときに別役実の童話「淋しいおさかな」を知る。影響あり。詩は書けず。安西水丸の漫画「青の時代」、鈴木翁二の影響を受ける。荒地派、櫂派、辻征夫、多田智満子を読む。詩は書けない。あるとき吉岡実の『詩を書きたい人は短歌を勉強してみるといい』という言葉に触れ、短歌を書くようになる。紀野恵、中城ふみ子、相良宏などの作品を好きになり歌を書き重ねる。詩を書けない日々がつづいたがのちに唐突に「カムパネルラ忌」「七夕」を書く。初めて「私」を失くす。もう森へは行かない。笹井宏之、杉﨑恒夫、小原奈実の短歌作品に興味を持ち、作歌をつづけた。 (著者の生前最後の文章 2021年6月24日) 【編者プロフィール】 野樹かずみ(のぎ・かずみ) 1963年愛媛県生まれ。1991年短歌研究新人賞受賞。歌集に『路程記』(2006)『もうひとりのわたしがどこかとおくにいていまこの月をみているとおもう』(2011)詩人の河津聖恵との共著に『christmas mountain わたしたちの路地』『天秤 わたしたちの空』(ともに2009)、蝦名泰洋との共著に『クアドラプル プレイ』(2021)。未来短歌会所属。広島在住。 著者 蝦名泰洋 編者 野樹かずみ 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年2月26日 B6判 192ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

石川信雄全歌集【新本】
¥3,080
【出版社内容紹介】 ポオリイのはじめてのてがみは夏のころ今日はあついわと書き出されあり(『シネマ』) モダニズム短歌の頂きをなす伝説の歌集『シネマ』で颯爽とデビューし、エスプリに満ちた瑞々しい歌で時代を駆け抜けた稀代のポエジイ・タンキスト、石川信雄。没後60年の節目についに明らかになる孤独なマイナーポエットの全貌。 モダニズム短歌を代表する伝説の歌集『シネマ』、トラブルのため50部しか刊行されず幻となった『太白光』のほか、退色した原稿用紙として発見され、今回初めて世に出る『紅貝抄』と歌集未収録歌をおさめる。 「短歌史の中で石川信雄は砂に埋もれていたコーナーストーンのような存在かもしれない。この礎石を発掘することにより、同時代の地層から煌めく鉱石が次々と姿を現すだろう。それらの群像に光が注がれるなら、現代短歌に至る道程の失われた断片が見つかるにちがいない」(編者あとがきより) 「今読んでも、というか、今読むからこそ強く感じる新鮮さは、作者の個性であると同時に、時代そのものの若さに根ざしたものでもあるのだろう。(略)新時代のポエジーへの強い希求が感じられる。現在の読者である私の目には、それ自体が眩しく映る」 ─────────穂村弘(栞より) 「定型に呼吸が寄りそうように置かれた言葉はとても自然で、現代の口語短歌の中に混じっていても違和感はあまりないだろう。(略)多数の歌集未収録作品も収載され、石川信雄が積み上げてきた作品世界が一望できる。その貴重さを喜びたい」 ─────────東直子(栞より) 「石川信雄の歌世界は知的遊戯を超えた詩的格闘の結露として、昭和の詩精神に輝きを添えている。(略)石川信雄の評価を大きく変える作品群であり、昭和モダニズムのひとつの到達であり、そして、新たな研究の出発点である」 ─────────黒瀬珂瀾(栞より) 【目次】 『シネマ』/『太白光』/『紅貝抄』/歌集未収録歌/戦地からの手紙/解題/石川信雄年譜/解説/編者あとがき 【収録歌より】 わが肩によぢのぼつては踊(をど)りゐたミツキイ猿(さる)を沼に投げ込む 『シネマ』 パイプをばピストルのごとく覗(ねら)ふとき白き鳩の一羽地に舞ひおちぬ 『シネマ』 すばらしい詩をつくらうと窓あけてシヤツも下着もいま脫ぎすてる 『シネマ』 人影のまつたく消えた街のなかでピエ・ド・ネエをするピエ・ド・ネエをする 『シネマ』 善よりは惡にかたむける人間(ひと)を載せ我が圓球(えんきゅう)は虚空(こくう)を旅す 『太白光』 磁石持ちて吸はるるごとく分け入ればミサンスロオプと告白すべき 『太白光』 天國のペンキ屋バケツに蹴つまづきニツポンの野山目のさめる秋 『太白光』 貝殻がぼくの胸にはたくさんある恋というはかない音をかなずる 『紅貝抄』 詩才などぼくは生れつき持たなんだ憂鬱(メランコリック)なライナァ・マァリァ・リルケの夢ばかり見き 『紅貝抄』 ひそかにも伝えられ来し言葉なれ我が誕生の夜の灯(ひ)にじむ 『紅貝抄』 【栞】 穂村弘「ポオリイとリュリュ」 東直子「空想と現実を往来する「まはだか」」 黒瀬珂瀾「「点」から「流れ」へ」 【著者プロフィール】 石川信雄(いしかわ・のぶお) 歌人、翻訳家。埼玉県出身。1908年、石川組製糸分家の長男として出生。第二早稲田高等学院・早稲田大学政経学部在学中に植草甚一らと英語劇に熱中し、文学に傾倒する。30年に筏井嘉一らと「エスプリ」を創刊。続いて「短歌作品」と「日本歌人」の創刊に参画。大学中退後、36年に第一歌集『シネマ』を刊行し注目を集める。同年に父が他界し、文藝春秋社に就職する。39年に応召。第五一連隊から江蘇省に派遣され、翌年支那派遣軍総司令部報道部に転属する。汪兆銘政権下の南京で、草野心平と中日文化誌「黄鳥」を発行。44年に土屋文明・加藤楸邨と中国大陸を横断する。戦後は多くの欧米文学者の小説を翻訳した。50年に第二次「短歌作品」を再刊すると同時に、「日本歌人」復刊に参加。54年に第二歌集『太白光』を発行。61年「宇宙風」短歌会創設。64年死去、享年56。 【編者プロフィール】 鈴木ひとみ(すずき・ひとみ) 京都市出身。石川信雄の姪。同志社女子大学卒業。ミネソタ大学、筑波大学大学院人文社会科学研究科、立命館大学大学院先端総合学術研究科で学ぶ。ヘイルストーン英語俳句サークル同人。共編著に『京都まちかど遺産めぐり』(ナカニシヤ出版)、『石川信雄著作集』(青磁社)、『黄鳥』(三人社)、『I WISH』ヘイルストーン英語俳句アンソロジー(代表編集スティーヴン・ギル)など。 著者 石川信雄 編者 鈴木ひとみ 発行所 書肆侃侃房 発行日 2024年12月15日 四六判 392ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

塚本邦雄歌集【新本】
¥2,860
【出版社内容紹介】 2025年で没後20年 日本脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係りも 前衛短歌運動によって新風をもたらし、古典からの流れを辿った博覧強記の知性で、韻律を改革し、独自の比喩を追求した、戦後短歌史を代表する歌人・塚本邦雄。 『水葬物語』『日本人靈歌』を完本で収録、塚本邦雄の短歌世界を一望できる1800首。編者による詳細な解説、年譜を付す。「新編歌集シリーズ」(全4巻)、これにて完結! 「〈魂のレアリスム〉に目覚めたそのまなざしは、誰よりもまっすぐに短歌の「現實」を見据えている。(略)塚本邦雄という方法をめぐって、その作品を一望できる本書の誕生に立ち会えたことを、こころから幸福におもう」 ─────────井上法子(栞より) 「塚本の歌はときに難解ではあるのだが、その先にあるメッセージ自体は、決して難しいものばかりではない。(略)純化ということの象徴としてその「たましひ」は限りなく澄みとおり、冷たい」 ─────────染野太朗(栞より) 「短歌プロパーでないひとが読んでも「前衛短歌」、ことに塚本邦雄はおもしろい」 ─────────吉田隼人(栞より) 【目次】 『透明文法 「水葬物語」以前』抄/『水葬物語』(完本)/『装飾樂句』抄/『日本人靈歌』(完本)/『水銀傳說』抄/『綠色硏究』抄/『感幻樂』抄/『星餐圖』抄/『蒼鬱境』抄/『靑き菊の主題』抄/『森曜集』抄/『されど遊星』抄/『閑雅空間』抄/『天變の書』抄/『歌人』抄/『豹變』抄/『詩歌變』抄/『不變律』抄/『波瀾』抄/『黃金律』抄/『魔王』抄/『獻身』抄/『閑雅空間』抄/『天變の書』抄/『歌人』抄/『豹變』抄/『詩歌變』抄/『不變律』抄/『波瀾』抄/『黃金律』抄/『魔王』抄/『獻身』抄/『風雅默示錄』抄/『泪羅變』抄/『詩魂玲瓏』抄/『約翰傳僞書』抄/解説(尾崎まゆみ)/塚本邦雄年譜 【栞】 井上法子「〈魂のレアリスム〉について」 染野太朗「にくしみとたましひ」 吉田隼人「ポータブル・塚本邦雄」 【収録歌より】 革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化してゆくピアノ(『水葬物語』) 五月祭の汗の靑年 病むわれは火のごとき孤獨もちてへだたる(『装飾楽句』) 日本脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係りも(『日本人靈歌』) 馬を洗はば馬のたましひ冱ゆるまで人戀はば人あやむるこころ(『感幻樂』) 夢の沖に鶴立ちまよふ ことばとはいのちを思ひ出づるよすが(『閑雅空間』) 【著者プロフィール】 塚本邦雄(つかもと・くにお) 1920年滋賀県生まれ。43年「木槿」入会「靑樫」同人となる。47年「日本歌人」の前川佐美雄に師事。51年第一歌集『水葬物語』刊行。中井英夫らの賛同を得て岡井隆、寺山修司らと前衛短歌運動を展開し戦後短歌に新風をもたらし、60年に一冊限りの同人誌「極」を創刊。以後も古典から現代短歌までの流れを遡り、美学や技法などを取り入れながら磨き上げ、短歌の可能性を追求。古今東西の文化や芸術などへの深い知識と教養に裏付けられた創作活動は、三島由紀夫に称賛されるなど、分野を超えて広く影響を及ぼした。85年歌誌「玲瓏」主宰となる。現代歌人協会賞、詩歌文学館賞、迢空賞、斎藤茂吉文学館賞、現代短歌大賞などを受賞。01年「塚本邦雄全集」完結。短歌、小説、評論、アンソロジーなど、その著書約300冊。05年6月9日歿。享年86。命日は「神變忌」。09年日本現代詩歌文学館に蔵書および遺品の一部が寄贈された。 【編者プロフィール】 尾崎まゆみ(おざき・まゆみ) 1955年愛媛県生まれ。1977年早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。1987年塚本邦雄に出会い師事。「玲瓏」入会。1991年第34回短歌研究新人賞受賞。現在「玲瓏」撰者 編集委員。神戸新聞文芸短歌選者、伊丹歌壇選者。歌集に、『微熱海域』、『酸つぱい月』、『真珠鎖骨』、『時の孔雀』、『明媚な闇』日本歌人クラブ近畿ブロック優良歌集賞、『奇麗な指』『 ゴダールの悪夢』。他にセレクション歌人12『尾崎まゆみ集』、『尾崎まゆみ歌集』現代短歌文庫132。歌書『レダの靴を履いて 塚本邦雄の歌と歩く』、共著『塚本邦雄論集』など。 著者 塚本邦雄 編者 尾崎まゆみ 発行所 書肆侃侃房 発行日 2024年11月1日 四六判 400ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

往信 / 佐々木朔【新本】
¥2,200
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 朗読をかさねやがては天国の話し言葉に到るのだろう ぼくの街、森、湖辺(うみべ)から きみの駅、埠頭、観覧車へと 連絡橋を渡っていく切手たち。そして鳩。 ──────飛浩隆 【収録歌より】 はるのゆめはきみのさめないゆめだからかなうまでぼくもとなりでねむる いちめんに銀杏つぶれラブコメの最後はかならずラブが勝つこと 関係を名づければもうぼくたちの手からこぼれてゆく鳳仙花 にしんそばと思った幟はうどん・そば 失われたにしんそばを求めて 香港の十分おきに雨が降る映画のなかの雨の香港 【栞】 川野芽生「過誤に殉じて」 榊原紘「あこがれ」 平岡直子「風穴」 【目次】 湖辺で 春睡綺譚 良い旅を あのひとに ラブ・コメディ そのあとの 夏の日記 ベリー・サマー 走る セオリー パーリデイ pro(f|c)essor 到達 rain radar 往信 探偵と天使 草津、湯畑のそば 具象と灯籠 まちあるき たばかり 橋と水/ペテルブルク 早春賦 百年前 【著者プロフィール】 佐々木朔(ささき・さく) 1992年生まれ。神奈川県横浜市出身。早稲田短歌会を経て、現在「羽根と根」同人。 著者 佐々木朔 発行所 書肆侃侃房 発行日 2025年2月28日 四六判 176ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

あおむけの踊り場であおむけ【新本】
¥1,980
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 犬の骨を犬のようにしゃぶりたいと妹の骨にも思うだろう 第4回笹井宏之賞大賞受賞! 自分のからだのなかに未知の窓がいくつも開くような独特の感覚にうろたえる。大胆につかみだされる言葉の弾力と透きとおって不穏な世界に惹きつけられる。 ━━━━大森静佳(栞文より) ここにある歌たちの静かで、人けを離れて、体と身の回りをあらためて見直すような、狭い世界の可能性を追究するような、ひっそりと楽しいあり方に対して私はリアルな共感を覚えずにいられない。 ━━━━永井祐(栞文より) 【収録歌より】 手のひらを水面に重ね吸い付いてくる水 つかめばすり抜ける水 夜の川に映る集合住宅は洗いたての髪の毛のよう 恐竜って熱いんだっけ 夏の夜に麦茶含んで口きもちいい 銀杏の葉踏みしめられて白い道あたまのなかみたいで抱きたいな おなかすいてないのにおなかが鳴っている椿を思い浮かべて落とす 【目次】 切り株の上 食物網 スムージー 身体の動かせるところ 浮石 ノウゼンカズラ 覆土 べにひかり 紙と皮 暗くなる前に日が暮れるだろう あとがき 【著者プロフィール】 椛沢知世(かばさわ・ともよ) 1988年東京都生まれ。「塔」短歌会所属。2016年、作歌を始める。第4回笹井宏之賞大賞受賞。第30回歌壇賞次席。 著者 椛沢知世 発行所 書肆侃侃房 発行日 2024年7月6日 A5判変形 128ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

埃だらけのすももを売ればいい / 高柳聡子【新本】
¥2,200
【出版社内容紹介】 詩集とはある世界観の具現であった ロシア文学におとずれた興隆期「銀の時代」(1890~1920年代)。ペテルブルクの古書店で偶然見つけた詩集を手がかりに、100年前の忘れられた15人の女性詩人たちのことばを拾い上げる。『女の子たちと公的機関』が増刷を重ねる著者による「web侃づめ」の好評連載が書き下ろしを加えて書籍化! 鮮烈である。もう埋もれさせはしない。忘れ去られ、あるいは神秘化された女性詩人たちの生き様と詩作を掬い出すかのようなこの本は、そんな祈りにも思える。 ━━━━━水上文 2024年2月全国書店にて発売予定です。 【「はじめに」より】 わずか15人しか紹介できないのだが、彼女たちの詩の向こう、言葉の向こう、生の向こうに、その他の無数の女性たちの声を感じ取っていただけたらとても嬉しい。戦争や革命のどよめきのなかで世界のあちこちに散らばっていき、今ではどこに眠っているのかわからない詩人も多い。だからこそ、同じ言語で詩を残した女性たちは、こうして一冊の書物の中に久方ぶりに集うことを喜んでくれるような気がしている。(高柳聡子) 【目次】 まえがき 1 遠い異国を見つめて アデリーナ・アダーリス 2 もっとも忘れられた詩人 マリア・モラフスカヤ 3 戦争と詩を書くこと アンナ・アフマートワ 4 詩は私の祈りである ジナイーダ・ギッピウス 5 二つの魂を生きて チェルビナ・デ・ガブリアック 6 私の身体は私のもの マリア・シカプスカヤ 7 誰も見ぬ涙を詩にして リュボーフィ・コプィローワ 8 風そよぐ音にも世界は宿り エレーナ・グロー 9 「女の言語」を創出せよ ナデージュダ・ブロムレイ 10 昼の太陽と幸福と、そして夜の闇と テフィ 11 すべての詩は啓示となる アデライーダ・ゲルツィク 12 わが歌は私が死んでも朝焼けに響く ガリーナ・ガーリナ 13 テクストの彼岸にいる私 リジヤ・ジノヴィエワ=アンニバル 14 ロシアのサッフォーと呼ばれて ソフィア・パルノーク 15 私は最期のときも詩人である マリーナ・ツヴェターエワ 「銀の時代」主要人物 参考文献 あとがき 【著者プロフィール】 高柳聡子(たかやなぎ・さとこ) 1967年福岡県生まれ。ロシア文学者、翻訳者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。おもにロシア語圏の女性文学とフェミニズム史を研究中。著書に『ロシアの女性誌━━時代を映す女たち』(群像社、2018年)、訳書にイリヤ・チラーキ『集中治療室の手紙』(群像社、 2019年)、ローラ・ベロイワン「濃縮闇━━コンデンス」(『現代ロシア文学入門』垣内出版、2022年所収)など。2023年にロシアのフェミニスト詩人で反戦活動家のダリア・セレンコ『女の子たちと公的機関 ロシアのフェミニストが目覚めるとき』(エトセトラブックス)の翻訳を刊行。 著者 高柳聡子 発行所 書肆侃侃房 発行日 2024年2月1日 四六判 184ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

花と夜盗 / 小津夜景【新本】
¥2,090
【出版社内容紹介】 英娘鏖 はなさいてみのらぬむすめみなごろし 現世(うつしよ)のカオスにひそむ言葉の華麗な万華鏡(ミクロコスモス) ────谷川俊太郎 『いつかたこぶねになる日』などエッセイでも活躍する俳人・小津夜景。 田中裕明賞を受賞した『フラワーズ・カンフー』に続く6年ぶりの第二句集。 2022年11月発売予定です。 【収録句より】 漣が笑ふいそぎんちやくの朝 蟬生(あ)れて死んで愛してゐた時間 莨火(たばこび)を消して裸足の身を焦がす 香水のちがふ白河夜船かな パピルスや死後千年の音階図 君の瞳(め)を泳ぐおらんだししがしら かささぎのこぼす涙をおつまみに 露実るメガロポリスよ胸も髪も 逃げ去りし夜ほど匂ふ水はなく 後朝のキリマンジャロの深さかな 【目次】 一 四季の卵 春はまぼろし 駒鳥の隣人 ルネ・マグリット式 カフェとワイン ポータブルな休日 狂風忍者伝 冬の落書き 花と夜盗 胸にフォークを 二 昔日の庭 陳商に贈る 貝殻集 今はなき少年のための AQUA ALLEGORIA 研ぎし日のまま サンチョ・パンサの枯野道 三 言葉と渚 水をわたる夜 夢擬的月花的(ゆめもどきてきつきはなてき) 白百合の船出 【著者プロフィール】 小津夜景(おづ・やけい) 1973年北海道生まれ。2013年「出アバラヤ記」で第2回攝津幸彦賞準賞、2017年句集『フラワーズ・カンフー』で第8回田中裕明賞を受賞。その他、著作に漢詩翻訳つきの随筆集『カモメの日の読書』『いつかたこぶねになる日』、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者・須藤岳史との共著『なしのたわむれ 古典と古楽をめぐる手紙』などがある。 著者 小津夜景 発行所 書肆侃侃房 発行日 2022年11月24日 四六判 146ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

まぼろしの枇杷の葉陰で 祖母、葛原妙子の思い出【新本】
¥1,760
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 「幻視の女王」とも評された、戦後短歌史を代表する歌人、葛原妙子。彼女には家族にしか見せなかった別の姿があった──。チャーミングで愛おしい、「異形の歌人」の横顔。 「おばあちゃんとのことについて、色々な人が色々なことを言っているだろう。あれはみんな違うんだよ」 「あたりかまわず朱と咲きいでよ」と自らを鼓舞し、脇目もふらず作歌にいそしんだ歌人、葛原妙子。 子どもの頃、大森の祖母の家に行く時には何か冒険に出かけるような気持ちになった。かつての病院の敷地内にあった、広い平屋住宅。周囲には枇杷の大樹が緑の葉をさかんに茂らせていた。 孫である著者から見た葛原妙子とは──。戦後短歌史を代表する歌人と、その家族の群像がここにある。 向田邦子、須賀敦子を髣髴とさせる、極上の名エッセイ集。 【本文より】 私は祖母のことを「おばあちゃん」と呼んではいたものの、祖母は世間一般で言う「おばあちゃん」らしさが感じられる人では全くなかった。夫にかしづき、家族を愛し、まめまめしく皆の世話をやいていた父方の祖母とあまりに違いすぎる。そのことに戸惑いを覚えつつも、ある種の諦めの気持ちがあった。 ***** 「おばあちゃんはカジンだから……」 周囲の大人たちがしばしば口にする「カジン」という音に、「歌人」という漢字があてはまることを知ったのはだいぶ後になってからだった。「カジン」にせよ「歌人」にせよ、同年代の子供たちが親しまないこれらの言葉は、大人たちから与えられた玩具のように、幼い私の傍らにいつもあった。 【目次】 ■はじめに ■大森の家 大森の家/祖母の思い出 ■祖母の生い立ち 葛原妙子の生い立ち/二枚の写真 ■軽井沢のこと 軽井沢のこと/眩しき金 ■朱と咲きいでよ ふたつの雛/朱と咲きいでよ/かけす/酒瓶の花/多擵のみづうみ/栗の木はさびしきときに/しずくひとつ、取りさった幸福/切手のこと/素晴らしき人生 ■室生犀星と祖母 イシのようなひと/畳の上の伊勢えび/實となりてぞ殘れる ■まぼろしの枇杷 銀靈/貞香と妙子/祖父の思い出/まぼろしの枇杷 ■あとがき 【著者プロフィール】 金子冬実(かねこ・ふゆみ) 1968年東京生まれ。旧姓勝畑。早稲田大学大学院で中国史を学んだのち、東京外国語大学大学院にて近現代イスラーム改革思想およびアラブ文化を学ぶ。博士(学術)。1995年より2014年まで慶應義塾高等学校教諭。現在、早稲田大学、東京外国語大学、一橋大学等非常勤講師。1996年、論文「北魏の効甸と『畿上塞囲』──胡族政権による長城建設の意義」により、第15回東方学会賞受賞。 著者 金子冬実 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年9月2日 四六判 184ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

現代詩ラ・メールがあった頃 1983.7.1 — 1993.4.1 / 棚沢永子【新本】
¥2,200
【出版社内容紹介】 今から40年前、ふたりの女性詩人が男性主導の文芸シーンに一石を投じるべく立ち上がった。 新川和江・吉原幸子責任編集「現代詩ラ・メール」の創刊である。 女性による女性のための詩誌創刊。 女たちの発表の場を作り出し、また新人たちを発見しはぐくみながら、詩の大海原を航海し続けた10年間。 笑いあり、涙あり、事件あり。ここで語られる数多の出来事は、単なる過去の思い出話ではない。現代にも繫がる熱きシスターフッドの物語である。 【目次】 ラ・メール誕生の夜 闘いのはじまり F氏のジレンマとA子のトラウマ 新しい人々 怒濤のごとく日々は過ぎ ウーマンズ・ライフ 失踪願望 しなやかに生きなさい 「おかえり」 新たなる海へ 魚たちは泳ぐ 名詩発掘 充実のとき 樹の種 こぼれ落ちてよ 顔 ゆがんでいるよ 毀れていく午後 それぞれの空へ 【著者プロフィール】 棚沢永子(たなざわ・えいこ) 1959年東京生まれ。大学卒業と同時に、ちょうど創刊された「現代詩ラ・メール」の編集実務を担当。鈴木ユリイカ責任編集の詩誌「Something」に、田島安江とともに編集人として参加。現在は夫婦で喫茶店を経営しながら、フリーで編集&ライター業。著書に『東京の森のカフェ』(書肆侃侃房)がある。 著者 棚沢永子 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年8月31日 A5判 256ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

寺山修司 彼と私の物語【新本】
¥2,090
【出版社内容紹介】 寺山修司没後40年 「青目……寺山のこと、好きだった?」 恋人、元妻、師、同志として、生涯を寺山修司のパートナーであり続けた九條今日子が、晩年に再会した著者にだけ開いて見せた思い出の小箱。誰にも見せることのなかった寺山の素顔に胸打たれる。 元天井桟敷の著者が綴る今は亡き九條今日子と寺山修司の物語。 誰かと話したくなる時がある。ふっと自分の心のうちを吐露したくなる日。九條さんにもそんな逢魔時があって、相手に選ばれたのが青目海だった。 本書で語られる九條さんの心うちは、生々しい。私には知り得なかったことばかりだ。会ったこともない女性像が立ち上がって驚いてしまう。それは青目海にとっても同じ体験だったのかも知れない。だからこそ書き残したかったに違いない。急に、九條さんに逢いたくなった。 ——萩原朔美(前橋文学館館長) 【著者プロフィール】 青目海(あおめ・うみ) 1946年、東京生まれ。劇団「天井桟敷」の創立メンバー。 19歳で構成作家に、以後、テレビドラマの原作、脚本を手がける。 独身時代のパリ、ローマに始まり、結婚後はカナダ、ニューヨーク、メキシコ、モロッコ、スペイン、最後の20年は南ポルトガルの小さな漁師町に暮らした路傍の主婦。2015年に帰国、伊豆在住。 脚本/「親にはナイショで」「東京ローズ」他。 舞台/「アカシヤの雨に打たれて」 著書/『私は指をつめた女』(文春ネスコ)、『南ポルトガルの笑う犬』 『リスボン 坂と花の路地を抜けて』(書肆侃侃房)など。 ********** 九條今日子(くじょう・きょうこ) 本名:寺山映子(てらやま・えいこ) 1935年、東京生まれ。三輪田学園卒業後、松竹音楽舞踊学校を経て、九条映子の名でSKD(松竹歌劇団)の舞台にデビュー。松竹映画に移り青春スターとして活躍し、寺山修司と出会い結婚。1967年「天井桟敷」をともに設立し、制作を担当。離婚後も劇団運営を続け、寺山亡き後もその遺志を継ぎ、精力的に活動に続ける。株式会社テラヤマ・ワールドの共同代表取締役として寺山作品の著作権管理を行い、三沢市寺山修司記念館名誉館長、三沢市観光大使をつとめる。2014年4月30日、肝硬変による食道静脈瘤破裂のため死去、享年78。 著書『ムッシュウ・寺山修司』『回想・寺山修司 百年たったら帰っておいで』。 寺山修司(てらやま・しゅうじ) 1935年、青森生まれ。1954年、「短歌研究」新人賞受賞。早稲田大学在学中より歌人として活躍。1957年、第一作品集『われに五月を』刊行。1967年、演劇実験室「天井桟敷」創立。劇作家・詩人・歌人として数多くの作品を発表し、演出家としても世界的名声を獲得。1983年5月4日、肝硬変と腹膜炎のため敗血症を併発し死去、享年47。 代表作、映画『書を捨てよ町へ出よう』『田園に死す』『草迷宮』『さらば箱舟』、演劇『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』『阿呆船』『邪宗門』『青ひげ公の城』『奴婢訓』『レミング―壁抜け男』、歌集『空には本』、詩集『地獄篇』、小説『あゝ、荒野』、エッセイ『家出のすすめ』『誰か故郷を想はざる』、評論集『地平線のパロール』などがある。 著者 青目海 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年8月16日 四六判 280ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

前川佐美雄歌集【新本】
¥2,640
【出版社内容紹介】 生誕120年! いますぐに君はこの街に放火せよその焔の何んとうつくしからむ (『植物祭』) 塚本邦雄、山中智恵子の師であり、「現代短歌の発端」として比類なき歌を紡いだ歌人・前川佐美雄。 代表歌集『植物祭』『大和』を完本で収録、前川佐美雄の短歌世界を見渡せる1600首。編者による詳細な解説、年譜を付す。 『葛原妙子歌集』(川野里子編)、『山中智恵子歌集』(水原紫苑編)に続く新編歌集シリーズの第3弾。 「前川佐美雄という人は、〈白痴〉の自由な境地に憧れを抱き、時には何かに憑かれたように物狂おしく歌いながらも、ついに一つの信念に溺れることのできない人だったのではないか。(中略)私はそのアンビバレントな佇まいと、それでいて〈ごまかしのちつとも利かない性分〉に、非常な魅力を感じるのである」 ─────────石川美南(栞より) 「ひとり野をゆき、萩の群れ咲くなかに自らの「たましひ」を見つめる孤高の歌人の姿が浮かび上ってくる。(中略)彼の歌業に一貫して流れているのは、「人間の歴史の最初」から人を、そして「われ」を捉えて離さない根源的な不安であり孤独であるだろう」 ─────────菅原百合絵(栞より) 「そのスパークの仕方に惹きつけられてすぐ好きになった。それまでに知っていた、たとえば戦後の名歌集にある緊張感やきびしさ、一首の格調、ゆるぎなさとはだいぶ違うもので、驚いたし、一人の思い込みだけれどなんとなくシンパシーを感じたのだった。(中略)前川佐美雄という優れた電波塔が送受信していたものを、わたしたちはその歌から受け取って、上手くいけば肌に感じるように体験することができるだろう」 ─────────永井祐(栞より) 【目次】 『春の日』/『植物祭』(完本)/『白鳳』/『大和』(完本)/『天平雲』/『日本し美し』/『金剛』/『紅梅』/『積日』/『鳥取抄』/『捜神』/『松杉』/『白木黒木』/『天上紅葉』/解説(三枝昻之)/前川佐美雄年譜 【栞】 石川美南「見える人は、見えない場所で」 菅原百合絵「野をゆく人の省察」 永井祐「佐美雄体験」 【収録歌より】 いますぐに君はこの街に放火せよその焔の何んとうつくしからむ(『植物祭』) 春がすみいよよ濃くなる真昼間のなにも見えねば大和と思へ(『大和』) 春の夜にわが思ふなりわかき日のからくれなゐや悲しかりける(『大和』) 火の如くなりてわが行く枯野原二月の雲雀身ぬちに入れぬ(『捜神』) 「おつくう」は億劫(おくこふ)にして億年の意としいへればこころ安んず(『白木黒木』) 【著者プロフィール】 前川佐美雄(まえかわ・さみお) 1903(明治36)年奈良県忍海村に代々農林業を営む前川家長男として生まれる。1921年、「心の花」に入会、佐佐木信綱に師事。22年、上京し東洋大学東洋文学科に入学、「心の花」の新井洸、木下利玄、石榑茂から刺激を受け、同年9月の二科展で古賀春江の作品に感銘、関心をモダニズムに広げる。30年に歌集『植物祭』刊行、モダニズム短歌の代表的な存在となる。33年奈良に帰郷、翌年「日本歌人」創刊、モダニズムを大和の歴史風土に根づかせた独行的世界を確立。占領期には戦争歌人の一人として糾弾されたが、『捜神』の乱調含みの美意識が評価され、門下の塚本邦雄、前登志夫、山中智恵子等が活躍、島津忠夫が現代短歌の発端を『植物祭』と見るなど、現代短歌の源流とされる。迢空賞受賞『白木黒木』からの佐美雄の老いの歌は人生的な詠嘆を薄めた融通無碍の世界である。1970年に奈良を離れて神奈川県茅ヶ崎に移り、1990年87歳で死去。 【編者プロフィール】 三枝昻之(さいぐさ・たかゆき) 1944(昭和19)年山梨県甲府市に生まれる。早稲田大学第一政経学部経済学科入学と同時に早稲田短歌会で活動、卒業後同人誌「反措定」創刊に参加。現在は歌誌「りとむ」発行人、宮中歌会始選者、日本経済新聞歌壇選者。歌集に『甲州百目』『農鳥』『天目』『遅速あり』他。近現代短歌研究書に『うたの水脈』『前川佐美雄』『啄木ーふるさとの空遠みかも』『昭和短歌の精神史』他、近刊『佐佐木信綱と短歌の百年』。現代歌人協会賞(1978)、若山牧水賞(2002)、やまなし文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞、斎藤茂吉短歌文学賞、角川財団学芸賞(2006)、神奈川文化賞(2010)、現代短歌大賞(2009)、日本歌人クラブ大賞(2022)、紫綬褒章(2011)、迢空賞(2020)、旭日小綬章(2021)他。2013年より山梨県立文学館館長を務める。 著者 前川佐美雄 編者 三枝昻之 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年8月31日 四六判 368ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

koro【新本】
¥2,310
【出版社内容紹介】 眼の奥に錆びた秤が一つあり泣けばわずかに揺れる音する 『悪友』で熱烈な支持を集める著者の、無二の進化を遂げた渾身の第二歌集。 【栞文より】 「救われたくない。ゆるされたくない。そう何度も叫んでいる。(中略)できれば全て脱ぎ捨てたいのだ。そうすればふたたび穢れず生きていける」(江戸雪) 「榊原の美意識は現代短歌において実に独自性が高い。そしてその根底には、神秘への思慕がある」(黒瀬珂瀾) 「この作家の器の大きさに感嘆した。自在な言葉が相応な重さを持って宇宙の謎に拮抗している。人間が人間である悲苦から逃げることなく、現代人の知性によって真っ向から対峙している。(中略)怖るべし・怖るべし・怖るべし」(水原紫苑) 【収録歌より】 銀漢に表裏があれば手触りは違うのだろう 指輪を外す 百合のように俯き帽子脱ぐときに胸に迫りぬ破約の歴史 額縁を焼(く)べてきたかのような貌ゆっくり上げてただいまと言う ボトルシップの底に小さな海がある 語彙がないから恋になるだけ ヘアバームのくらいにおいだ泣くのなら最初の一粒から見ていたい 【栞】 江戸雪「滅びの思考」 黒瀬珂瀾「かずかぎりなきあなたとわたし」 水原紫苑「宝剣の一行」 【著者プロフィール】 榊原紘(さかきばら・ひろ) 1992年愛知県(三河)生まれ、奈良県在住。第2回笹井宏之賞大賞受賞、第31回歌壇賞次席。2020年、第一歌集『悪友』刊行。短詩集団「砕氷船」の一員。 著者 榊原紘 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年8月31日 四六判変形 208ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

ニューヨークの唇【新本】
¥2,200
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 月を追う途中の子どもにあいさつをさよならみたいな青いハローを 流星のように去っていった蝦名泰洋の 最後の短歌とメッセージ 闘病のすえ、両吟『クアドラプル プレイ』の友・野樹かずみに託した遺稿をもとに、多くの声援を受けて編まれた歌集。 歌集『イーハトーブ喪失』も収録 【収録歌より】 落ちている海かと思うあおむけの君がまぶたをひらいた瞳 抱きあげるするとわたしも何者かに抱きあげられていることを知る 夕焼けがより濃い席で答えなき答え合わせを待つ女の子 この鍵はどこのドアにも合わないが永久があるから失くしたくない 全校の運動会に人が消えひとりで踊るオクラホマミキサー 【著者プロフィール】 蝦名泰洋(えびな・やすひろ) 1956年青森県生まれ。 あるとき吉岡実の『詩を書きたい人は短歌を勉強してみるといい』という言葉に触れ、短歌を書くようになる。 1993年沖積舎より歌集「イーハトーブ喪失」出版。1994年伊丹イタリアの筆名による私家版で詩集「カール ハインツ ベルナルト」出版。 2021年7月26日 永眠 著者 蝦名泰洋 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年6月11日 四六判 192ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

『女人短歌』 小さなるものの芽生えを、女性から奪うことなかれ【新本】
¥2,420
【出版社内容紹介】 わたしたちの短歌誌をつくろう! 女性のために女性自身の手によって編まれた歌誌『女人短歌』。第二次大戦の敗戦直後に創刊され、48年にわたって刊行された。 男性中心の歌壇のなかで結社を超えて女性たちが結束し、相互研鑽に努めた。女性歌人が活躍できる地平を切り拓いた功績は大きい。 五島美代子、長沢美津、生方たつゑ、阿部静枝、山田あき、葛原妙子、中城ふみ子、森岡貞香ら、『女人短歌』に集った歌人たちの熱き魂のリレーを追う。 歌誌『女人短歌』について初めての総合的研究書。 著者 濱田美枝子 発行所 書肆侃侃房 発行日 2023年6月26日 四六判 320ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955