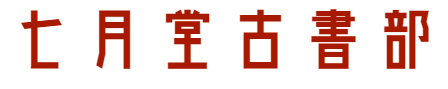-

花魂〈ソウル〉 / 橋本由紀子【新本・七月堂書籍】
¥2,750
橋本由紀子幻想コラージュ詩集 花は恋する 花は生殖する 永遠を求めて 【作品紹介】 庭の時間 ダリアの匂いは 消えた庭の夏の匂い 囲われた土庭で繰り返し花は咲いた 不思議ないのちのにおいを 新聞紙に包んで 幼稚園にはこんだ 夏風と秋風の日 吸い上げる時間 消化されていく時間 去っていったにおい もう手にいれられない 記憶の中の 若い父と母の庭の時間 誰もいなくなっても ダリアは球根を育てている 新聞紙に包まれた ことのある 生命の匂い 著者 橋本由紀子 発行所 七月堂 発行日 2025年11月10日 135×220mm 150ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955

-

美人画の書き方【古本】
¥3,700
SOLD OUT
【状態】 函欠、パラフィン付 <カバー> ヤケ有 <本体> 経年劣化によるシミヤケ有、ワレ有 著者 伊東深水 発行所 崇文堂 四六変型判 150ページ __________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

紙片の宇宙 シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本【古本】
¥1,400
SOLD OUT
【状態】 <カバー> 小汚れ有 編集 ポーラ美術館学芸部 発行所 ポーラ美術館 発行日 2014年9月21日-2015年3月29日 190mm×250mm 178ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

活動芸術論 / 卯城竜太【古本】
¥2,400
【状態】 カバー、帯付 <カバー> スレ、上部ヨレ有 著者 卯城竜太 発行所 イースト・プレス 発行日 2022年7月22日 A5判 576ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

東松照明と沖縄 太陽へのラブレター【古本】
¥8,500
【状態】 カバー:ヨレ小、裏表紙ヨゴレ小、裏表紙左角折れ目有、背表紙角破れ小 著者 東松照明 発行所 大和プレス 発売元 水声社 発行日 2011年9月22日 355mm×260mm 215ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

素描画誌 第二号 ほどける手【新本】
¥1,100
SOLD OUT
このたび七月堂は、古井フラの詩画集「素描画誌」第二号「ほどける手」を刊行いたします。 ↓詳細はこちらnoteにて↓ https://note.com/shichigatsudo/n/n346f6dffa245 ↓「素描画誌」創刊号の詳細はこちら↓ https://note.com/shichigatsudo/n/nc1e2633ba9ca 創刊号「色のない花」お買い物はこちらから https://shichigatsud.buyshop.jp/items/97349523 「描くこと」や「空白」について、深く思索し実践した、画詩文一体の作品集。3ヶ月ごとに全10回の刊行を予定しております。 第2号のテーマは「ほどける手」。 本作は詩と素描画とエッセイで構成されています。 「わたし」というたった一つのものを握りしめて生きること、緩やかにほどき広がっていくこと。 ゆっくりとお楽しみいただけましたら幸いです。 手といえば、「素描画誌」は七月堂社内で印刷し、一冊一冊スタッフの手によって糸綴じ製本をしております。 ほどける・握りしめる、といった、手の動きのような心の往来は、生きる上でとても大切なことです。そしてわたしたちが特に心がけた方がよいのは、ゆるめてほどけることではないでしょうか。握りしめることは充分すぎるほど、幼いころからやってきたのですから。 ーーー素描画誌「ほどける手」より引用 著者┆古井フラ 絵・装幀・組版┆著者 印刷・製本・発行┆七月堂 A5判・糸綴じ 32ページ 価格 1,000円+税 発行 4月22日 発売 4月20日 ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

クレ-の絵本【新本】
¥1,760
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 40点の絵と14編の詩が奏でる二重奏(デュエット) クレーの色彩世界に谷川俊太郎の詩が重なる。 スイスが生んだ今世紀最高の画家クレー。音楽理論を融合させた詩情あふれる色彩世界に触発された詩人が紡ぎだすイメージ豊かな言葉が、新しい画集の形を提示する。 絵 パウル・クレー 詩 谷川俊太郎 発行所 講談社 発行日 2025年2月14日(第36刷) 200mm×175mm 62ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

湖畔地図製作社【新本】
¥2,970
【出版社内容紹介】 湖をわたって異世界へ――雨、波紋、等高線、球体、大航海時代 博物学的指向をともにするふたりが響きあう、 なんとも摩訶不思議な書物が誕生! スコープオブジェ×短篇小説 幸福なコラボレーション! 水辺のほうへ―― 〈おおよそ15分で対岸の桟橋につきます。そこへボートをつなぎ、道なりにお進みください。微高地のうえの建物が当社です〉 スコープオブジェ51点収録。 横長の函入り美麗本! 【スコープ scopeとは】 桑原弘明が手がける唯一無二の金属性の〈覗き箱〉的オブジェ。スコープをのぞけば、ほのかに人の気配が漂う部屋や廃墟や、庭が見えてくる。箱のなかにわずか数ミリの机や家具が設えられた、超微小の博物学的世界。 【著者プロフィール】 長野まゆみ (ナガノマユミ) 東京生れ。1988年『少年アリス』で文藝賞受賞。2015年『冥途あり』で泉鏡花文学賞、野間文芸賞受賞。『テレヴィジョン・シティ』『猫道楽』『鳩の栖』『箪笥のなか』『チマチマ記』『デカルコマニア』『ささみみささめ』『団地で暮らそう!』『兄と弟、あるいは書物と燃える石』『フランダースの帽子』『銀河の通信所』『さくら、うるわし』『カムパネルラ版銀河鉄道の夜』『45°ここだけの話』などがある。 近著は『長野まゆみの偏愛耽美作品集』『ゴッホの犬と耳とひまわり』 公式HP http://www.mimineko.co.jp 公式X(Twitter)耳猫風信社 桑原弘明 (クワバラヒロアキ) 1957年茨城県生れ。多摩美術大学油画科卒業。1980年代より極小のオブジェ作品を制作。1995年巖谷國士の序文を得て渋谷アートスペース美蕾樹で初個展。2000年ギャラリー椿で個展。2001年種村季弘の序文を得てスパンアートギャラリーで個展以降、毎年年末にギャラリー椿とスパンアートギャラリーで交互に個展を開く。その他グループ展、美術館での展示多数。著書に『スコープ少年の不思議な旅』(巖谷國士・文)、『Scope 桑原弘明作品集』。 著者 長野まゆみ 発行所 国書刊行会 発行日 2024年1月25日(2刷) 四六判横 128ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

素描画誌 創刊号 色のない花【新本】
¥1,100
SOLD OUT
このたび七月堂より、古井フラ画詩文『素描画誌』を刊行することとなりました。 年4回、全10回の発行を予定しております。 記念すべき創刊号は、「色のない花」。 詩と散文と素描画から構成される本誌は、七月堂社内でオンデマンド機にて印刷をし、製本もスタッフにて行っています。 毎号100部の限定発行の予定ですが、創刊号は200部の発行となります。 『素描画誌』は、2020年1月に、古井フラさんが自主制作されたものが始まりとなります。 その時は、一冊で完結している雑誌でしたが、内容は同じように、詩と散文と素描で構成されていました。 コロナ禍にそれを手にし、クロッキーが訓練や習作上、修正や消すことのできないという意味において、「消すことができないということは、失敗は残り、失敗は許されている。そこでは成功も失敗も、行為においては等価である」という一文に強く心を射抜かれました。 古井さんの定義するところの「素描」には、主に線描、単色で表した絵の他に、「対象を観察した写生」「線描を主とした描画」「画材は紙と鉛筆、コンテ等」「無彩色」「基本的に決して描き直しをしない」「短時間の描画」(1~10分程度)というものがあって、古井さんの散文を読み進めると、「短時間の描画」という刹那的な瞬間に惹かれていく自分の視線に気がつきます。 時間で測れる瞬間というのは、本当はどれも、立ち上がってはすぐ過去になってしまう「点」のひとつ。 その点を、1秒とみるのか、1分とするのか、10分とするのか。 それによって出現する「瞬間の景色」は、陰影も輪郭も変わってくるのだろうと思います。 ただどの瞬間も、限られているという決まりのなかではすぐに消えてしまうものであり、それを切り取った描画は、すでに過去にあったものである、という事実とともに、しかし、今も生き生きと目の前にあり続けることの存在感と不思議さと哀しみ。 古井さんの意識のなかには、過去、現在、未来、と絶え間なく流れる時間という大きな川が流れていて、たった今、五感で感じとどめられるものを素描画にしている。 そう思ってフラさんの絵を見ると、今日という一日がどれだけ大事であるか。成功も、失敗も、大きな川の流れのなかでは小石くらいのことでしかないかもしれず、よくも悪くも手元に留めておくことはできないのだろうなと思うのです。 そんな風に形にして留めてはおけないからこそ、流れていくなかにおいてもなお、心に残るものたちと少しでも多く触れ、大事にして暮らしていきたい。 古井さんの素描画を見るにつれ、「一瞬」という目には見えない時間の流れを可視化してくれているように思い、あなたはなにを信じたいの?という問いが立ち上がってくるように感じます。 うまく答えられる日もあれば、ない日もあって、それらすべてが愛おしい瞬間だと思えるような。 描くことは、その名を消していくこと ある花を描くことで、その花の固有名詞を消していく この世の形をうつすこと それはつくるというより とどめること そしてとどめることには 一抹の哀しみがある 素描画誌「色のない花」より 著者 古井フラ 発行所 七月堂 発行日 2025年1月22日 A5判 28ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955

-

はたらく本屋【新本】
¥2,420
【出版社内容紹介】 「はたらく」って、なんだろう? 朝から晩まで、 ひとつの職業の人にはりついて、 その仕事や暮らしぶりを見つめてみた。 大人と子どもがともに読みながら 「はたらく」ことの意味を考える あたらしい写真絵本シリーズ(総ルビ)。 ■シリーズのことば 「将来、なにになりたい?」 大人は子どもになにげなく質問します。 答えはさまざま、時代のうつりかわりとともに 人気の職業があるようです。 しかし、サッカー選手でも花屋でも、 おなじ職業だからといって、 おなじようにはたらき暮らしている人はいません。 ぼくらの生活は、だれかの仕事のおかげで 成り立っているはずなのに、 彼らが日々なにを思い、 どんなふうにくらしているのかはあまり知りません。 夜道で足をとめて星空を見上げるように、 目の前を通りすぎる いろんな「はたらく」を見つめたい。 大人も子どももおなじ地平に立って、 はたらくってなんだろう、と考えてみる。 そんなふうにして、 このシリーズをつくりたいとおもいます。 ■推薦のことば ●ミロコマチコ(絵本作家) この世界は、みんなの一日、一日でできている。 履いている靴も、休憩時間に食べるごはんも、 お昼寝するときに使う枕も。 たくさんの人の“はたらく”とともに暮らしている。 わたしの“はたらく”もきっとだれかにつながってる。 嬉しくなって、ああ、明日もはたらこうって思う。 ●鳥羽和久(教育者) 生きることは社会とつながること。 そして社会とつながることは、 はたらく人とつながることだ。 つながる人とは気持ちいい関係でいたい。 そのためには、たがいにすがすがしい仕事がしたい。 この本には、 はたらくことのすがすがしさが詰まっていて、 生きるようにはたらくことをぼくたちに教えてくれる。 ■シリーズラインナップ ※本シリーズ(最初の4冊)は、 リトルプレスの出版レーベル Ambooksから刊行されていた リソグラフ版をもとにオフセット印刷で 大判にして新装刊行するものです。 ・2024年9月刊行予定 ◆はたらく本屋 ◆はたらく中華料理店 ・2024年11月刊行予定 ◆はたらく製本所 ◆はたらく図書館 ・2025年2月刊行予定 ◆はたらく動物病院 ◆はたらく庭師 ■はたらく本屋 大阪にあるちいさな本屋「長谷川書店」は、 子どもからお年寄りまで 地域の人たちに愛される町の本屋さん。 朝、お店のなかでは、とどいたばかりの 新しい本がぎっしりつまった箱がいったりきたり。 いそげいそげ、もうすぐ10時。 お客さんがやってくる--。 【プロフィール】 [写真]吉田 亮人(ヨシダ アキヒト) 1980年宮崎県生まれ。京都市在住。滋賀大学教育学部卒業後、タイで日本語教師として1年間勤務。帰国後小学校教員として6年間勤務し退職。2010年より写真家として活動開始。2023年に写真集出版社「Three Books」を設立し共同代表を務める。著書『Brick Yard』(私家版)、『The Absence of Two』(青幻舎・Editions Xavier Barral)、『しゃにむに写真家』(亜紀書房)など。第47回木村伊兵衛賞2023最終候補、日経ナショナルジオグラフィック写真賞2015・ピープル部門最優秀賞、コニカミノルタ・フォトプレミオ年度大賞など受賞多数。 [著]矢萩 多聞(ヤハギ タモン) 画家・装丁家。1980年横浜生まれ。9歳から毎年インド・ネパールを旅する。中学1年で学校を辞め、ペンによる細密画を描きはじめる。南インドと日本を半年ごとに往復し暮らし個展を開催。2002年から本づくりにかかわるようになり、これまでに600冊を超える本の装丁をてがける。2012年、京都に移住。現在は本業のほか、Webラジオ、リトルプレス、ワークショップなど、本とその周辺を愉快にすべく活動中。著書『本とはたらく』(河出書房新社)、『美しいってなんだろう?』(世界思想社)、『本の縁側』(春風社)など。 著者 矢萩 多聞 写真 吉田 亮人 発行所 創元社 発行日 2024年9月10日 B5判変型 24ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

旅の心を取り戻す(サイン本あり)【新本】
¥2,090
柊有花 詩画集 このたび柊有花さんによる、「絵」と「言葉」の本を刊行いたします 明け渡してしまった 自分の心を取り戻すには 目的のない旅が必要だ 【作品紹介】 「呼吸」 人が去ったあとの海は 清らかに 打ち上げられた星は 浜一面にまたたく しなやかに編まれた 太陽の光は 海の底を明るく 照らしている 水面はやわらかに逆立ち 一枚の葉を 浜へ運んでゆく 一艘の白い舟が 岸を目指し進み かもめは追いかけ飛んでゆく 白い半月のかなた 昼の まぼろしのように浮かび ひとり 夜を待っているのか 濃い青と ブルーグリーンのあいだ 海は 海はたえまなく 呼吸している 【著者からのメッセージ】 絵と言葉の本を作りたいとずっと思っていました。わたしにとって絵は仕事でもあり、ライフワークでもあります。けれど言葉もまた欠かすことのできない大切なものです。絵と言葉は分かちがたくつねに影響しあっていて、それを自分らしい形で統合していきたいといつも考えてきました。けれど絵本や詩集など、自分の思うものを収めるにはすこし形が違うように思えて、自分が作りたいものはなんなのかさえわかりませんでした。作りたいと思うものを形にできないことは、わたしにとってとてもつらいことです。そのことが恥ずかしく、自分に対して怒りと悲しみを感じていました。 コロナ禍の内省の時間を経て、わたしがものを作ることへの意識はずいぶん変わったように思います。そのなかで2020年に作った画文集『花と言葉』に背中を押され、もっと遠くへ旅に出たいと思うようになっています。けれど同時に不安があります。家にいることに慣れてしまった自分はそんな旅へ出られるのかしら、と思うのです。 今回刊行する本が、そんな自分のなかの葛藤を打破するようなものになっているかはわかりません。けれど、自分の現在地をあらわしたものであることはまちがいないと確信しています。旅の途上の、悩み、怒り、悲しみ、進みたいと願う、未完成で等身大の自分です。 旅は楽しく面倒なもの。わたしたちにはかけがえのない日常があり、コントロールできない環境があり、いつでも旅に出られるわけではありません。けれど旅と日常のあわいに立って自分の心を眺める時間、それもまたひとつの旅なのだと思います。わたしが誰かの本を通じて自分の心をたしかめているように、この本も誰かにとってのちいさな旅への扉となることがあったら。そんな願いをこめながら、力を貸してくださるみなさまとこの本を届けられたらと思っています。 著者・装画・挿絵 柊有花 発行所 七月堂 発行日 2024年10月5日 138×148mm 88ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955

-

『AM 4:07』ポストカードセット(4枚1セット)
¥800
【内容紹介】 七月堂zine『AM 4:07』(創刊号)の付録として作られたポストカードを、4枚1セットにして販売いたします! 写真:寺岡圭介(紙片店主) ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

英国の本屋さんの間取り【新本】
¥1,980
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 いい人生を送るために、もっと本屋さんに行こう。 愛される書店の秘密を探るこの本が、 そんなふうに思うきっかけになってくれたら、 とてもうれしい。 (本書「はじめに」より) イギリスでは、独立系書店の数が過去6年連続で増加し、 20年以上にわたって続いていた書店減少の傾向が確実に反転したと言われます。 電子書籍やオンライン書店ももちろん普及しているなか、 なぜ人々は、本屋さんで本を買いたくなるのでしょう――。 そこには、毎日でも通いたい、友達にも紹介したいと思わせる 納得の店づくりがありました。 本屋さん好き、街歩きが好き、 イギリスの街並みが好き、カフェめぐりが好きな人も必見! 『世界で最も美しい書店』、『世界の美しい本屋さん』他、 多数の“本屋さん本”を手掛けてきた著者が インタビューと間取りレポートから読み解く、写真とイラスト満載の一冊です。 <目次> 英国の本屋さん 見せ方の工夫、愛される工夫 ロンドンが誇る世界で最も美しい本屋さん ドーント・ブックス 本と人が行き交う駅 バーター・ブックス 運河に浮かぶ船の本屋 ワード・オン・ザ・ウォーター 多様な町のインクルーシブな書店 レビュー 至高のビジュアル本専門店 メゾン・アスリーン 偶然の発見を楽しむ迷宮 リブレリア ケンブリッジの文化生活を支える店 ヘファーズ 独立系書店リバイバルの火付け役 ジャフェ・アンド・ニール 歴史を誇る名門大学運営の店 ケンブリッジ・ユニバーシティー・プレス書店 気鋭の建築家・デザイナーが競演 タッシェン・ストア・ロンドン 小さな読者を大きく育てる店 アリゲーターズ・マウス 世界遺産の植物園にある書店 お風呂もある本の殿堂 ミスター・ビー・ズ・エンポリアム 誰をも歓迎するLGBTQ+書店 ゲイズ・ザ・ワード 天井まで本が積み上がる老舗 オープン・ブック アナーキーな仲間が集う本屋 カウリー・ブックショップ 〝独立国家〞の伝説は今も リチャード・ブース 画家と作家が経営する町の本屋さん インク@84 親子のような二人が作り上げる店 バーリー・フィッシャー 著者 清水玲奈 発行所 エクスナレッジ 発行日 2024年7月2日 A5判 160ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

植物の部屋 モノ・ホーミー線画集②【新本】
¥770
SOLD OUT
【内容紹介】 本書は架空の植物を描いた新作の線画13点を収録した作品集です。 貝がら千話および未発表作品から、植物に関するおはなし13篇を併録しています。 著者 モノ・ホーミー 発行所 BODESTONE 発行日 2024年7月4日(第2刷) A6判 ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

上野リチのレターブック【新本】
¥2,200
【出版社内容紹介】 昨年東京・丸の内の「三菱一号館美術館」で開催された回顧展には、女性を中心に大勢の来場者が訪れました。 そんな今注目の上野リチのデザインやアートの数々が、満を持してレターブックとして登場! どのページをめくっても、今なお斬新さを感じるデザインに目を奪われること必至です! レターブック初! 巻末に使い勝手のよい「ミシン目入り一筆箋」収録。 編集 芸術新聞社 発行所 芸術新聞社 発行日 2023年2月21日 A5判 136ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

詩と絵のアクリルブロック「場末にて」
¥6,380
【商品説明】 西尾勝彦著『場末にて』の詩を用いたアクリルブロックです。 背景画は『場末にて』装画を担当された小川万莉子さんによるもの。 アクリルブロックの全面に「詩」を、背面に「絵」を印刷しているので文字が浮かんで見え、影が絵に映る様子もとても綺麗です。 *詩は『場末にて』収録「公園」より抜粋 詩 西尾勝彦 制作 七月堂 サイズ 100mm×100mm×20mm 詩集はこちらより https://shichigatsud.buyshop.jp/items/78700815 ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

セザンヌの犬【新本】
¥1,980
【出版社内容紹介】 いくつものときとばしょが 生きものや物たちのもとで折りたたまれてはひらかれ だれもしらない思弁的な時空間が この体のなかに降りてくる --------------------- 画家・評論家など多方面で活躍する著者が「自分のすべてがここに入っている」と語る、小説の新たな可能性を示す驚くべき初小説集。 連続講座、展覧会の開催にあわせ、ついに刊行。 『群像』『早稲田文学』『ことばと』などで発表された作品に、書き下ろしを加えた計7作品を収録。 [著者] 古谷利裕 Toshihiro Furuya 1967年生まれ。画家、評論家。1993年東京造形大学卒業後、画家として2002年「VOCA展」(東京)、2004年「韓国国際アートフェア・日本現代美術特別展」(ソウル)、2008年「組立」(埼玉)、2011年「第9回アートプログラム青梅」(東京)、2015年「人体/動き/キャラクター」(東京)など、各所で活躍。 評論家としても、美術・小説・映画・アニメなど特定のジャンルに限らない活動を展開。『世界へと滲み出す脳』(青土社、2008年)、『人はある日とつぜん小説家になる』(青土社、2009年)、『虚構世界はなぜ必要か? SFアニメ「超」考察』(勁草書房、2018年)など多数の著書が刊行されているほか、2010年~2019年には「東京新聞」美術評を、2020年には「文學界」新人小説月評を担当。 1999年11月には、自身のホームページにて「偽日記」(https://furuyatoshihiro.hatenablog.com )を開始。以降「はてなブログ」への移転を挟みつつ24年以上にわたって連日更新されている同ページは、ひとりのアーティストの長期的な日記として、また日本の芸術・思想の特異なアーカイブとして、小説家・保坂和志をはじめ多くの人々から高く評価されている。近年は、「社会的チートの撲滅&死の恐怖からの非宗教的解放」をテーマとする集団「VECTION」(https://vection.world )の主要メンバーとしても活動。 著者 古谷利裕 発行所 いぬのせなか座 発行日 2024年6月17日 111mm×163mm 304ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

2464 LITTLE MAGICAL HOMIES【新本】
¥1,650
【著者内容紹介】 「2464 LITTLE MAGICAL HOMIES」のすべての鉛筆画作品38点と、その制作背景にあたるカード占いの結果一覧を収録した作品集をTOUTEN BOOKSTOREさんでの展示にあわせて刊行致しました。 展示のカタログではありますが、作品にタイトルでも解説でもない言葉を一言添えて、絵本のような仕上がりになりました。 著者 モノ・ホーミー 印刷・製本 イニュニック 発行日 2024年4月29日 120mm×120mm 44ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

ヒグチユウコ ボリス カードブック
¥1,870
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 日本のみならず世界から注目されている画家・ヒグチユウコが描く、愛猫・ボリスをモチーフとした作品ばかりを24枚の大判ポストカードとして収録したポストカードブック。 前作『ヒグチユウコ ポストカードブック』からの再録が3点、新規掲載21点を収録。 著者 ヒグチユウコ 発行所 グラフィック社 発行日 2022年5月25日(初版第1刷) B6変形 48ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

すきになったら【新本】
¥1,540
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 すきになったら、しりたくなる。あなたのすきなものを、すきになったり、あなたにとって大事なものを理解したくなる。すきになったら、いっしょに笑いたいし、あなたの悲しみをしりたくなる。だって、いっしょにいたいから......「すき」っていう気持ちは、これまでの世界の見え方を変えてしまうほどのパワーがある。読む者の感情を揺さぶる、ずっと大切にしたい絵本。 著者 ヒグチユウコ 発行所 ブロンド新社 発行日 2024年2月5日(第14刷) 220mm×205mm 32ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

新装版 BABEL【新本】
¥5,940
【出版社内容紹介】 世界的人気の画家・ヒグチユウコが「バベルの塔」のブリューゲル、ボスの世界をヒグチの世界観で描き下ろした渾身の画集。函、扉、エングレービング、奥付が新しくなり新装版として登場。 著者 ヒグチユウコ 発行所 グラフィック社 発行日 2024年5月 A4判 32ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

Higuchi Yuko Artworks ヒグチユウコ作品集【新本】
¥2,970
SOLD OUT
【出版社内容紹介】 女子を中心に圧倒的人気の和紙にペン画で描くイラストレーター、ヒグチユウコ待望のファースト作品集。 作品のほか、ホルベイン、EmilyTemple cute、ユニクロ、資生堂、ninita、メラントリックヘムライト、あちゃちゅむなどとのコラボレーション作品の原画多数、巻末にはペン画のハウツー、アトリエ紹介、本人による詳細な作品解説も収録、決定版作品集です。 ファンのみならず、イラストレーターを目指す若い方々が見ても、ペンの筆跡まで再現する作品で、きっと勉強になるでしょう。 著者 ヒグチユウコ 発行所 グラフィック社 発行日 2024年4月25日(第21刷) B5変形 160ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

TEMPURA【古本】
¥2,000
SOLD OUT
【状態】 洋書(フランス)、良好 編集 Emil Pacha Valencia 発行所 TEMPURA 発行日 2022年 210mm×280mm 194ページ ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955
-

Who's who【古本】
¥3,000
【状態】 限定500部、箱付き 箱少し凹みあり 編集 那須孝幸 発行所 東京パブリッシングハウス 発行日 2010年10月1日 200mm×200mm ________________________________________ ※送料の変更をさせていただく場合がございます。詳しくは以下のURLよりご覧ください。 https://note.com/shichigatsudo/n/n848d8f375955